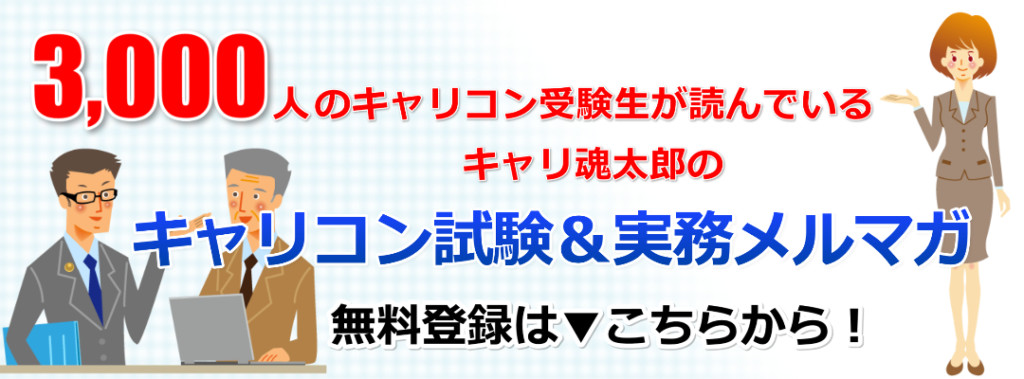資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。
このエントリーでは、村上春樹の「ノルウェイの森」を発達課題の観点から考察しています。
Contents
「僕」はキズキと直子の発達課題達成のための、モデリング対象として選ばれた。
こちらのエントリーを読む前に、↓を読んでおくとさらに理解が進むかもしれません。
「ノルウェイの森」では、発達課題を達成できなかった人々が、自ら命を絶っていきます。
これがまさに、ハヴィガーストやエリクソンの言った、「発達課題を達成できないと、人は不幸になる」、「その後の発達課題の達成も困難になる」という言葉のとおりであり、また「死者との邂逅」を選んだりする理由になっているんですね。
既に上記のリンクでお伝えしたように、直子とキズキは発達課題を回避したまま、高校生になりました。
そして、直子とキズキは、生まれ落ちたときから双子のような関係であったため、性的な関係を同年代の男女のように構築できないことに気づきます。
エリクソンの発達課題で言えば、不信感、恥・疑惑、罪悪感、劣等感を持たず、(男女の)役割の混乱が生じているんですね。
この辺りは、例えば直子の言葉や「僕」のモノローグにあるように、
キズキにはたしかに冷笑的な傾向があって他人からは傲慢だと思われることも多かった
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
「私たち、お互いの身体を隅から隅まで見せあってきたし、まるでお互いの体を共有しているような、そんな感じだったのよ」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
いつも自分を変えよう、向上させようとして、それが上手くいかなくて苛々したり悲しんだりしていたの。とても立派なものや美しいものを持っていたのに、最後まで自分に自信が持てなくて、あれもしなくちゃ、ここも変えなくちゃなんてそんなことばかり考えていたのよ。可哀そうなキズキ君
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
というように、劣等感が他者との関係においては比較的少ないこと、男女交際における恥や罪悪感の概念を持たずに成長したこと、そして「(最後まで)自分に自信が持てない」など、「自我同一性拡散」の状態に陥っていることが分かります。
そして、この「苛々」は、実は直子にも向けられています。
キズキは、直子のことを愛しているにも関わらず、同年代の男女と同じような性的関係を確立できないために、なんとか自分(と直子)を変えようとしているのですが、この時点では直子はキズキほどは深刻に考えていない節があるからです。
これは直子の、
「でも正直に言って、私はあの人の弱い面だって大好きだったのよ。良い面と同じ面くらい好きだったの。」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
という言葉からも分かります。
「弱い面を変えたい」と思っている人に「弱い面も好き」と言っても、なかなか伝わらないですよね。
この考え方は、支援者と相談者にも当てはまります。
支援者がいくら「ありのままのあなたで良い」と言ったところで、相談者は「(問題の解決のためには)変わらなきゃいけない」と考えていることがあります。
例えば、拒食症なども、そういった「ありのままの自分」を拒否し、変わりたいと考えている一つの例だと考えられます。
なんとか変わりたいと考えているキズキは、通常の男女関係をモデリングするために、主人公である「僕」に接近します。
モデリングはここでは、「観察学習」として捉えるほうが良いですね。
それが分かるのが下記の「僕」のモノローグです。
「僕は一人で本を読んだり音楽を聴いたりするのが好きなどちらかというと平凡な目立たない人間で、キズキがわざわざ注目して話しかけてくるような他人に抜きんでた何かを持っているわけではなかったからだ」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
特殊な才能などがあったり、もともとモテる人だと、モデリングの参考にしづらいと考えたのでしょう。
つまり、キズキが直子と一般的な男女関係を構築するために、キズキは「平凡な同学年の男性」を選ぶ必要があったのです。
その「平凡な同学年の男性」である「僕」が、同じく同学年の女性とどのように、性的な関係を構築していくのかを「モデリング」するために。
だから、キズキは下記のように、「僕」に言ったのです。
「今度の日曜日、ダブル・デートしないか?俺の彼女が女子校なんだけど、可愛い女の子つれてくるからさ」と知り合ってすぐにキズキが言った。
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
よく読むとここに「すぐ」という言葉があります。
通常、知り合ったばかりの友人を、「すぐ」に、ダブルデートに誘うことはありませんよね。
普通は「よく知って」から、「自分の彼女に会わせても大丈夫だな、自分の彼女の友達にも紹介して大丈夫だな、自分の友人はいい奴なのに、彼女がいないなんてもったいないな」というような思考を経て「ダブルデート」を企画し、誘うからです。
この「すぐ」という言葉からも、キズキが「「僕」がどのように女性と仲良くなり、性的関係を含む恋人関係を構築していくのか」を、モデリングしようとしていたことが分かります。
当然、悪い意味で考えれば、直子も「共犯者」です。
自分の友達を、「彼氏が連れてきたよく知らない男友達」に紹介することは、普通は乗り気にならないですよね。
つまり、このキズキの意図を知っていたことになります。
とはいえ、このモデリングは「僕」が直子の連れてくる女の子と合わないために失敗します。
「可愛くはあったけど、僕には少々上品すぎた。僕としては多少がさつではあるけれど気楽に話の出来る公立高校のクラス・メートの女の子たちのほうが性にあっていた。直子のつれてくる女の子たちがその可愛らしい頭の中でいったい何を考えているのか、僕にはさっぱり理解できなかった」
(中略)
そんなわけでキズキは僕をダブル・デートに誘うことをあきらめ、我々三人だけでどこかに出かけたり、話をするようになった。
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
この失敗の過程で、キズキはおそらく「僕」が直子を好きになるなら、その過程をモデリングしてみることも検討したのだと思います。
だから彼は、文字通り必死で
「三人でいると彼は直子に対しても僕に対しても同じように公平に話しかけ、冗談を言い、誰かがつまらない思いをしないようにと気を配っていた」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
のです。
通常、生まれ落ちたときから双子のように仲の良かった幼馴染と、気の合うクラスメイトと3人で過ごすのに、そんな気遣いをする必要はありません。
逆に言えば、キズキには、直子にとっても、「僕」にとっても、一緒にいる空間を居心地よくしなければいけない理由があったんですね。
さらに「僕」のキズキ評を読むと、こうあります。
「もっとも彼は決して社交的な人間ではなかった。彼は学校では僕以外の誰とも仲良くはならなかった。あれほど頭が切れて座談の才のある男がどうしてその能力をもっと広い世界に向けず我々三人だけの小世界に集中させることで満足していたのか僕には理解できなかった。」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
この涙ぐましい努力…
もともと社交的ではないキズキが、必死で三人の小世界を(直子と「僕」が)居心地のよいものにしようとしていたことが伺えます。
方法論の是非はおいておいて、キズキが本当に直子を愛していたことが分かるモノローグですね。
ただ、直子にとっては下記のように、キズキ君との時間がより好ましいものになるだけだったので、こちらも失敗に終わりますが…
「あなたとキズキ君と三人でいるのけっこう好きだったのよ。そうすると私もキズキ君の良い面だけ見ていられるでしょ」
ノルウェイの森©村上春樹 講談社
作者である村上春樹本人が、「ノルウェイの森」を「100%の恋愛小説」と評した理由。
このように、ノルウェイの森は、「発達課題の達成」が重要なテーマとして取り上げられています。
なぜ作者である村上春樹自身が、この「ノルウェイの森」を、「100%の恋愛小説」と評したのか。
それは、世評とは真逆の、「プラトニックな恋愛」であることを訴えたかったからではないでしょうか。
この「ノルウェイの森」でプラトニックだった二人、それは「直子とキズキ」そして「僕と緑」です。
そして100%と言えるのは、もちろん「直子とキズキ」しかありません。
「僕と緑」は、打算的な部分が多少あるからです。
発達課題を達成しているということは、言い換えれば「大人になる」ということです。
大人、つまり打算的な部分が生じてしまう以上、通常の発達課題を経ているとプラトニックな、100%純粋な恋愛はできません。
この「ノルウェイの森」は、発達課題を達成できなかったが故の「直子とキズキの100%プラトニックな恋愛」を小説化したものだったんですね。
私の大学時代の友人は、「ノルウェイの森」を「エロ小説」と評したわけですが、さもありなん。
発達課題とその回避(未達成)の問題が理解できて初めて、「ノルウェイの森」の主人公が「僕」ではなく「キズキ(と直子)」になるからです。
キズキと直子は、一度も性的関係を持っていないのだから、「ノルウェイの森」は主人公であるキズキと直子の観点で読むと「エロ小説」にはなりえないんですね。
 |
![]()