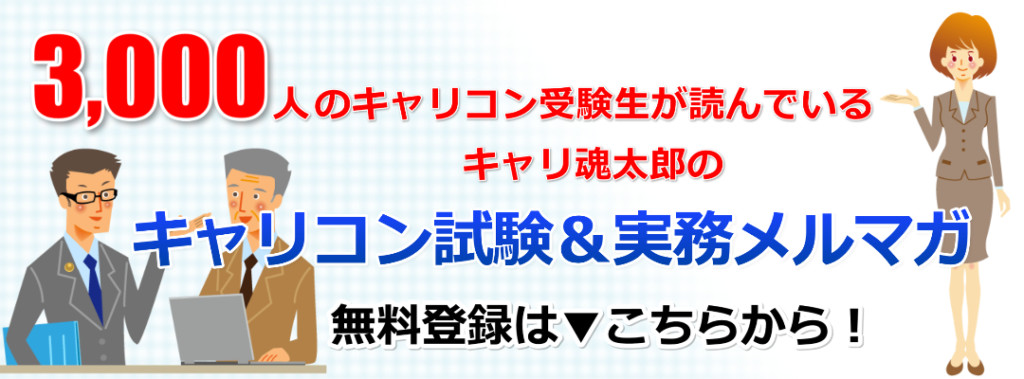このエントリーでは、キャリアコンサルティングにおける「アドバイス」や、職業能力開発促進法上の「助言及び指導」の解釈、そして実際のキャリアコンサルティングでの実践について解説しています。
Contents
良いアドバイス、ダメなアドバイスと助言・指導の解釈
 加藤さん
加藤さんついつい、アドバイスをしてしまうクセがあり、養成講習の同期や講師から、注意されてしまいます。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎ふむふむ。ついついアドバイスをしてしまうんですね。ちなみに、どんなアドバイスをしているんですか?
 加藤さん
加藤さんえ、どんなアドバイスって…そうですね、「まずは夫婦で今後を相談してみるのはどうでしょうか」とか…
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎なるほど。それは「良いアドバイス」かもしれませんね。
 加藤さん
加藤さん良いアドバイスと、ダメなアドバイスがあるんですか?
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎ええ。そもそも職業能力開発促進法上、キャリアコンサルティングは「助言と指導」であることはご存じですよね。
 加藤さん
加藤さんはい。それはまあ学科は合格しているので、知っています。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎アドバイスが全てダメなら、この「助言と指導」はできないということになりますよね。
 加藤さん
加藤さんそうですね。確かに。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎とはいえ、この「助言と指導」は、そのまま「助言と指導」と解釈してはいけないんです。
 加藤さん
加藤さんどういうことですか?
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎実は「カウンセリング」という言葉は、法律上そのまま使えないんですね。なので「助言と指導」という言葉をあてているんです。
 加藤さん
加藤さんへぇ~知りませんでした。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎なので、例えば公認心理師法でも「心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」(公認心理士法第2条)
とされており、ここでも「助言と指導」なんですね。
 加藤さん
加藤さん公認心理師と言えば、カウンセラーの国家資格ですよね。その公認心理師法でも、「助言と指導」なんですね。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎はい。しかしここで言われる「助言と指導」は、いわゆる辞書に載っている「助言と指導」という言葉を意味するものではありません。
 加藤さん
加藤さんちょっとよく分かりません。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎法律には、その条文の「解釈」が必要なんですね。
例えば、公認心理師必携テキストでは、ここでの「助言」は「アドバイス」ではない。とされています。引用すると
「一般に誤解されているようなアドバイスという言葉から連想される「簡便で、即効性のある」あるいは「どこにでもありがちな、一般的・常識的な」ものでも一方的なものでもない。ここで求められている「助言、指導その他の援助」とは、クライエントの特性やプロセスに応じたきめ細やかなものである」
(引用:公認心理師必携テキスト第2版 学研メディカル秀潤社 P4)
クライエントへのアドバイスが、支援者の常識つまり準拠枠に沿ったものや、一般的な価値観によるものではなく、クライエントに寄り添い、その気持ちを受容し、話を聴いた結果の「提案」や「情報提供」であるならば、それは「行ってよいアドバイス」になるんです。
 加藤さん
加藤さんなるほど…同じ「夫婦でよく相談したら」という言葉でも、適当に話を聴いたうえでの言葉なのか、しっかり丁寧に傾聴を行ったうえでの言葉なのかによって、良し悪しが変わるということなんですね。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎その通りです。なので一律にアドバイスがダメ、というものではありません。個別の状況に応じた判断になりますね。
アドバイスは、「ついつい」できるような軽いものではない。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎あと、講座ではいつもお伝えしていますが「専門家」の言葉は、クライエントにとってはとても重いものです。
 加藤さん
加藤さんはい…
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎ついつい、なんて気軽にできるものではありません。時にはそのアドバイスが原因で、大きな損害が発生することもあるわけですから。
 加藤さん
加藤さん確かに…
クライエントの専門家はクライエントである。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎そして、クライエントの専門家はクライエントです。我々はクライエントのことを何も知らないという姿勢を忘れないことも大事ですね。
「指導」にしろ「気づきを与える」や「認知のゆがみを修正する」にしろ、どこか傲慢さ、マウント感を感じる言葉だと思いませんか?
 加藤さん
加藤さんそういわれると、そういう言葉も口頭試問でよく使ってしまいます…
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎言葉には、無意識的にその人の準拠枠が表れてしまうものです。言葉には気を付けていきたいですね。
 加藤さん
加藤さんええ…クライエントの人生を左右してしまうこともあると考えると、軽率な点があったことは否めないと思います。
 キャリ魂太郎
キャリ魂太郎それが理解できればOKです。
最後に、アドバイスに対して、クライエントが常に「自律した選択」ができることも大切ですね。
些細な一言が、クライエントの人生の大きな転機になってしまうこともあります。
クライエントに対してきめ細やかで寄り添った、そして専門家として適切な助言やアドバイス、そして提案になっているか、よく考えて伝えてくださいね。
 加藤さん
加藤さん分かりました。しっかりと話を聴いて、きちんと考えたうえでのアドバイスを肝に銘じます。