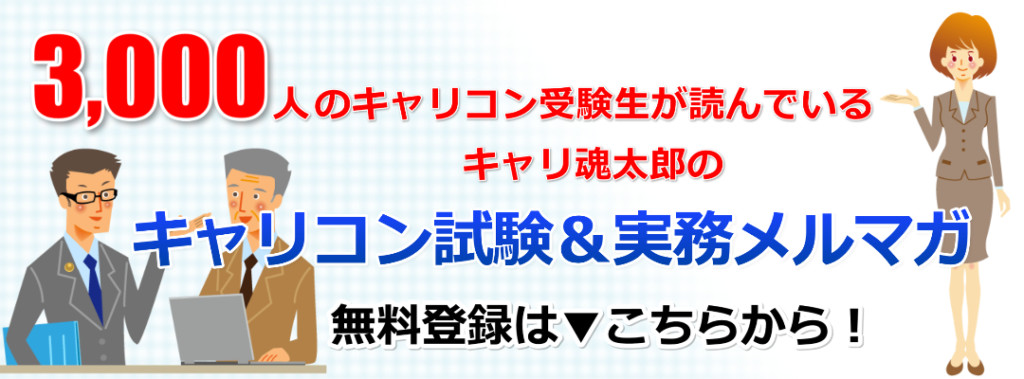このエントリーでは、誤解されがちな「解決志向」と「問題志向」の2つのアプローチの違いについて、クライエントの応答を用いて解説しています。
Contents
解決志向アプローチと問題志向アプローチの違いとは?
解決志向アプローチも、問題志向アプローチも、「傾聴」がベースであることは全く同じです。
この点を勘違いして「キャリアコンサルタントが解決する」と思い込んでいる方が多いのは、勉強不足としか言いようがありません。
繰り返しになりますが、「解決志向」は「リソース(資源)」に着目し、クライエントの話を聴く(ことが多い)、「問題志向」は「問題」に着目し、クライエントの話を聴いている(ことが多い)、ただそれだけの違いですが、当然クライエントの話す内容は大きく変わります。
また、キャリアコンサルタント業界での「問題志向」の場合、「クライエントの話を伝え返す」ことに重点を置いた面談構成を行うことが多いため、カウンセリング初学者には非常に取り組みやすく、有効なアプローチの一つです。
それに対し、「解決志向」は「クライエントのリソースを探索する」ための「問いかけ」が大きなポイントとなるアプローチですので、「意識した訓練」を行わなければ身に付かない実践的アプローチと言えます。
問題志向アプローチと解決志向アプローチの具体的な違いとは?
クライエント事例である「加藤さん」の応答から、問題志向アプローチと解決志向アプローチの具体的な「応答の違い」をご紹介します。
解決志向アプローチ勉強会にご参加されている方は、ご自身の逐語録チェックの参考にして下さいね。
※このエントリーの「問題志向アプローチ」の応答例は、解決志向キャリアコンサルティング勉強会に参加されている方の逐語録をベースにしています。なお、参加者は全てキャリアコンサルタント(2級キャリアコンサルティング技能士含む)です。
例1
 加藤さん
加藤さんいきなり営業から人事に異動したんで、もちろん人事の仕事って全くわかりませんので…部下に助けてもらいながらですね、仕事を一つ一つ覚えていくっていうか、そんな感じでしたね。
問題志向アプローチ例(伝え返し)
 土本さん
土本さんそうなんですね。部下にいろいろ教えてもらいながらお仕事を進めてこられたということなんですね
解決志向アプローチ例
➡「部下に助けてもらいながら」をフォーカス(伝え返し)
➡「関係構築スキル」をリソースとして捉える
➡「自然」「短期間」を入れることで、スキルの高さを強調
例2
 加藤さん
加藤さんスーパーに卸していたのですが、やっぱり、いまのニーズをちゃんと聞いた中で商品を提供するという、スーパーとの人間関係というか、人脈もありますし、そういうスーパーに卸すという仕事はやりやすいのかなと思いますね。
問題志向アプローチ例(伝え返し)
 土本さん
土本さんスーパーとの人間関係、人脈もあって、スーパーに卸す仕事はやりやすいのかなと。
解決志向アプローチ例(加藤さん=早坂さん)
➡「労働市場で評価されるリソース」として捉える。
例3
 加藤さん
加藤さん今こういうコロナの状況もあるんで、在宅も含めてですけど、やっぱり話する人もね、限られていますし、うん。ちょっとどんよりしてる感じですね。
問題志向アプローチ例(問題に着目)
 土本さん
土本さんそうすると、ちょっとどんよりっておっしゃってましたけれども、どんよりっていうのはどういう、やっぱり喋る人がいないからなのでしょうか?
解決志向アプローチ例
➡「どんより」を「シビア」に(言い換え技法)
➡「話をする人は限られる」を「限られた人が話している」に(言い換え技法)
例4
 加藤さん
加藤さん誰にも相談はしてないんですけども、誰にも相談できないから、それでここに来ました。
問題志向アプローチ例(問題に着目)
 土本さん
土本さん相談できないと思われているのは、どんな点でしょうか。
解決志向アプローチ例
➡「これまでの経験(リソース)」を探索
➡「相談できない」を「相談せず」に(言い換え技法)
「問題」に着目するより、「リソース」に着目する。
いかがだったでしょうか。
「伝え返し」はフォーカスするためにピンポイントで行い、「リソース」を探索するために問いかける。
「どんよりしている原因」「誰にも相談していない原因」といった「問題」にフォーカスを当てるかどうかはケースバイケース。
それよりも、とにかく「現在の状況に役立てることのできるリソース」を探索する。
これが「解決志向キャリアコンサルティング」です。
改めて強調しておきますが、「解決志向」は「キャリアコンサルタントが解決する」のではありません。
傾聴によって「解決のためのリソース探索」を支援しているだけです。
解決志向と問題志向は、「クライエントの『今、ここ』の状態に合わせて使い分ける
そして、解決志向と問題志向は、どちらかだけ、ではなく面談の中で刻一刻変化する、「クライエントの『今、ここ』の状態に合わせて使い分ける」これが大切です。
辛い話を聴いて欲しいのに、それを聴いてくれないのであれば、解決志向でもラポールは生まれません。
解決志向であろうと、ベースは当然「傾聴」なんですね。
余談ですが、キャリ魂塾では「クライエントに全神経を集中する」という、キャリコン業界でよくある指導は行いません。
クライエントの刻一刻と変化する「今、ここ」に合わせて、「自らのアプローチ」も変化させ、また「言い換え技法」など、「自らの応答の内容」、そして自らの自己一致・不一致にも意識を向ける必要があるからです。
 |
|
新品価格 |
![]()