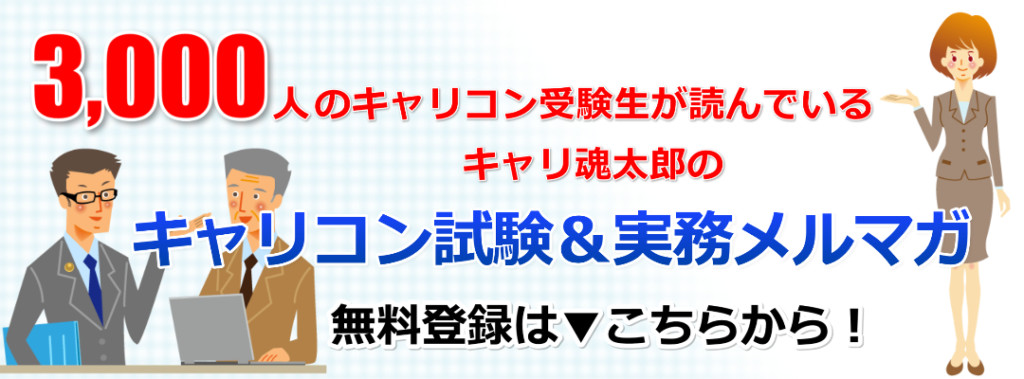資格で理想のライフスタイルを実現する、キャリ魂塾のキャリ魂太郎です。
このエントリーでは、なぜ「自己決定権」が尊重されなければならないか(そして「尊重」に留まる理由)を解説しています。
Contents
自己決定権とは何か。
「自己決定権の尊重」は、全てのキャリアコンサルタントが知っている言葉です。
しかし、「自己決定権」とは何でしょうか。
これを根拠に基づいて説明することのできるキャリアコンサルタントは、1級技能士まで含めても、恐らく極めて少ないのではないでしょうか。
当然のことですが、これは勉強不足とかそういった話ではありません。
元々試験科目にないこと、更に言えばキャリアコンサルタントを含めたカウンセラー業界が、法律的な在り方ではなく、心理支援的な在り方を重視してきた経緯があります。(なおキャリアコンサルタントと兼業されることの多い社労士でも、憲法は試験科目に入っていません)
「心」と「法律」は、ときには相反するものであり、その際に「心」を重視する傾向(「法律なんて言っていたら、この子は救われないのよ!」というようなアプローチですね)が強いことは、あなたも感じるのではないでしょうか。
自己決定権とは、
自分の生き方や生活について、他者からの介入を受けずに自由に決定する権利。
出典:Wikipedia
とされています。
出典がWikipediaであり、法律や判例ではない理由としては同じくWikipediaに下記のように記載されています。
自己決定権を憲法から導き出そうとすれば、それは日本国憲法で言えば第13条の幸福追求権から導き出せるものであり、文言からすれば「公共の福祉に反しない」限りにおいて尊重される。しかしながら、ある特定の行為を自己決定権として裁判で明言することは、そのことについて権利としての先例を作ることになり、司法の側には困難が伴う。現時点で、自己決定権を正面から認める最高裁判所判例は存在しないとされる。
出典:Wikipedia
弁護士であり、司法試験等の資格試験対策講座を開講されている、伊藤塾の伊藤真先生は、
「個人の尊重は、個人が一定の私的事項について、公権力による干渉を受けずに自ら決定することの保障を含むと解され、これを自己決定権(ないし人格的自律権)とよぶ。」
出典:伊藤真 試験対策講座5 憲法
と述べています。
 |
|
新品価格 |
![]()
自己決定権が「尊重」に留まる理由
なぜ、自己決定権は「尊重」されるに留まるのでしょうか。
この自己決定権が問題になる場面として、例えば下記のようなものがあります。
・自己の生命・身体の処分に関わる問題:安楽死、自殺、治療拒否等
・家族の形成・維持の問題:結婚、離婚、出産等
・ライフスタイルの問題:服装、家屋建築等
このように考えると、「服なんて着たくない!」という自由と、「他人の裸なんて見たくない!」という自由は当然衝突しますよね。
「自己決定権」が無制限に認められると、「個人の自由」が対立・衝突し、社会的秩序や国家維持の観点から望ましくないものがあることが分かります。
憲法第22条1項:職業選択の自由
なぜキャリアコンサルタントは「(キャリア形成において)自己決定権を尊重」しなければならないのか。
法律的な観点からみると、「憲法に幸福追求権や職業選択の自由がある」からです。
キャリアコンサルタントとして、最も重要なこの法理を教えていない養成講習が多数あります。
これも、「キャリアコンサルタントが心理支援を重視する民間資格」であったことに起因するものと思われます。
現在のキャリアコンサルタントは、法律に基づく国家資格者であるため、本来はコンメンタール※などが必要ですが、今のところ職業能力開発促進法にはコンメンタールがないため、私の考察ということで解説を行っています。
※コンメンタールとは、ドイツ語で「注釈書」を意味する言葉であり、条文の意味内容の正確な理解をするために必要となります。これは法律を学ぶ上で最も大切なこととされます。
憲法第22条1項は、「何人も、公共の福祉に反しない限り、…職業選択の自由を有する」と規定し、職業選択の自由を保障しています。
職業選択の自由とは、自分自身が就く職業を決定する自由です。
職業とは
では「職業」とはなんでしょうか。
私の学んだ養成講習では、この最も大切なことについても、講義や解説が(もっと言えばテキストへの記載も)ありませんでした。
そして、職業能力開発促進法にも、「職業」が定義されていません。
youtuberは職業でしょうか?
ブロガーは?
アフィリエイターは?
これらは職業でしょうか。それとも職業ではないのでしょうか。
仮に職業である・職業ではない、ならばその根拠は?
この問いに、法的な見地から答えられるキャリアコンサルタントを養成していない養成講習もあるのです。
判例による「職業」の概説
職業という概念について、判例は
「人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の活動たる性質を有し、各人が自己の持つ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである」(薬局距離制限事件 最大判昭和50.4.30)
このように述べています。
つまり先述のYouTuberやアフィリエイター、ブロガー、さらには旅人であろうが吟遊詩人であろうが、まず「自己の生計を維持するためにする継続的活動」であるかどうか、という文言で考えてみることが重要となります。
そう考えると、「職業に就く」というよりも「自己の生計を維持できる継続的活動となりうるかどうか」が、「職業」であるかどうかという判断基準の第一歩と考えられます。
更に、判例は「職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、様態においても原則として自由であることが要請される」と述べています。
これにより「職業選択の自由」には「職業活動の自由」も含まれるとされています。
職業選択の自由があるから、どんな職業でも就けるのか?
では、職業選択の自由があるから、どんな職業にでも就けるのでしょうか。
残念ながら、そうはなりません。
職業選択の自由の限界からみた「尊重」の理由
職業選択の自由に制限が加えられる根拠として、下記のような考え方があります。
1.職業は性質上、社会的相互関連性が大きいため、無制限に職業活動を許すと、社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じる恐れが大きい。
2.現代社会の要請する社会国家の理念を実現するためには、政策的な配慮に基づいて、積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくない。
(芦部P211)
1.により、最近話題の転売ヤーは規制されるケースがあることになります。転売を無制限に認めると、米騒動にまで発展してしまうことになるため、社会生活に不可欠な公共の安全が脅かされることになりますよね。
また、古物商なども盗品売買市場を形成しやすいため、規制されているように、多くの職業は2.の観点からも「自由に就く」ことができません。
こういった理由からも、自己決定権は「尊重」に留まるということになります。
おまけ:言葉が心を超えない理由
言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど、心に勝てない
(CHAGE&ASKA「SAY YES」)
というフレーズがあります。
なぜ「言葉は心に勝てない」のでしょうか。
法律的な理解で言えば、表現の自由(言葉)は内心の自由(思想・良心の自由=心)を超えることはないからです。
キャリ魂塾では、養成講習が教えない、「法律実務家」「コンサルタント」としての在り方、そして傾聴だけではない「心理療法」を指導しています。
 |
|
新品価格 |
![]()